礼拝メッセージ:中通りコミュニティ・チャーチ
離婚に関する教え
イエス・キリストの生涯シリーズ68
マタイによる福音書19章1節〜12節
(2024年2月25日)
離婚について、イエス・キリストとパリサイ人が議論している場面です。イエスは離婚の問題に限らず、神の教えに対して私たち人間が陥りがちな間違いを取り上げています。
礼拝メッセージ音声
参考資料
1節の「ヨルダンの川向こう」とはヨルダン川東岸地域のことで、ペレヤと呼ばれていた地方です。3節の「パリサイ人」は、ユダヤ教の一派であるパリサイ派に属する人のことです。モーセの律法以外に大量の細かい規則を作ってそれを守り、民衆にも守るよう教えていました。パリサイ人の多くは、イエスさまのことを救い主だと認めていませんでした。
5節は、創世記2:24の引用。
7節は、申命記24:1を念頭に置いた言葉です。
イントロダクション
私たちが神さまの用意してくださっているすばらしい人生を送っていくためには、神さまの教えを守り、神さまと良い関係でいることが大切です。今回の箇所で、イエスさまはパリサイ人と離婚について議論しておられます。しかし、イエスさまは単に離婚問題だけでなく、人間が神さまの教えに対して間違った態度を取りがちだということを暗に指摘しておられます。
私たちが神さまのみこころの内を歩んで、神さまと良い関係を保ち、結果としてこの地上でも死んだ後も祝福された人生を送るために、今回の箇所をご一緒に学んでいきましょう。
1.パリサイ人との議論
パリサイ人からの質問
イエスの移動経路
(1節)イエスはこれらの話を終えると、ガリラヤを去り、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方へ入られた。イエスさまは、ガリラヤ地方とサマリア地方の間で活動していらっしゃいました。そこを離れるとヨルダン川の東に渡り、南下して川の西側、ユダヤ地方に戻ってこられました。
いやし
(2節)すると大勢の群衆がついて来たので、その場で彼らを癒やされた。ペレヤ地方の人たちが、大勢イエスさまについてきました。そして、イエスさまはその人たちの中の病気の人や障がいを抱えた人、悪霊に取りつかれて苦しんでいる人などをいやされました。
この頃のイエスさまは、イエスさまのことを救い主だと信じない人の前ではほとんど奇跡を行なわなくなっていました。ですから、いやしの奇跡をイエスさまが行なわれたということは、ペレヤ地方の人たちが信仰を持っていたということです。
離婚に関する質問
(3節)パリサイ人たちがみもとに来て、イエスを試みるために言った。「何か理由があれば、妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。」ところが、イエスさまを救い主だと認めない人たちも紛れ込んできました。イスラエルの霊的な指導者であるパリサイ人たちです。
彼らはモーセの律法についてイエスさまに質問しました。それは、理由があれば妻と離婚しても良いかという問いです。
離婚に関するモーセの律法の教えは以下の通りです。(申命記24:1)人が妻をめとり夫となった後で、もし、妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、
この頃のパリサイ派は、大きく2つのグループに分かれていました。
- 非常に厳しく律法を解釈して守ろうとするシャンマイ学派
- 比較的ゆるい律法解釈をするヒレル学派
- シャンマイ学派は、この「恥ずべきこと」とは妻が姦淫を犯したということだと主張しました。つまり、浮気以外の理由で離婚することはできないという立場です。
- ヒレル学派は、姦淫に限らず夫が妻を気に入らなくなったらどんな理由でも離婚できると主張しました。たとえば、食事がまずいといった些細な理由でもOKです。
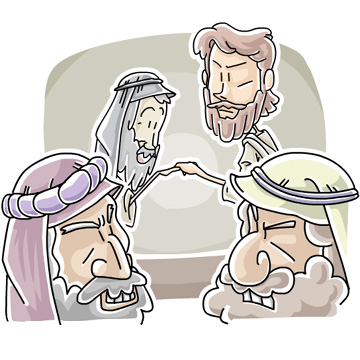
パリサイ人たちの狙い
パリサイ人たちの狙いは何だったのでしょうか。パリサイ人たちは、自分たちよりもイエスさまの方が人気があることをねたんでいました。そこで、ペレヤから大勢の人たちがイエスさまについてきたことを苦々しく思っていました。
このペレヤの人たちも、自分に律法を指導してくれたラビ(律法の教師)によって、シャンマイ学派とヒレル学派に分かれていました。ですから、離婚についても2通りの考え方をする人たちがそこにいたわけです。
もしもイエスさまがシャンマイかヒレルかどちらかの立場を明確にしたなら、そうでない方の人たちは幻滅してペレヤに帰って行くかもしれません。
もっとひどい企み
また、もっと悪辣な企みがあったと考える学者もいます。ペレヤ地方は、ガリラヤ地方と同じくヘロデ・アンティパスという国主の領土でした。バプテスマのヨハネの首を切って殺した人です。ヘロデがヨハネを逮捕したのは、ヨハネがヘロデの離婚と結婚について批判したからです。ヘロデはすでに妻がある身でありながら、自分の兄弟の妻だったヘロディアという女性と不倫関係になりました。そして、それぞれ配偶者と離婚して結婚したのです。
もしかしたらパリサイ人たちは、離婚というセンシティブな問題についてイエスさまの発言を引き出すことで、ヘロデの怒りを招いてやろう、あわよくばバプテスマのヨハネと同じように逮捕されたり殺されたりすればいいと考えていたのかもしれません。
いずれにしても、純粋な動機で質問したわけではないということです。では、それに対してイエスさまはどのようにお答えになったでしょうか。
イエスの回答
創世記からの教え
(4-6節)イエスは答えられた。「あなたがたは読んだことがないのですか。創造者ははじめの時から『男と女に彼らを創造され』ました。そして、『それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、ふたりは一体となるのである』と言われました。ですから、彼らはもはやふたりではなく一体なのです。そういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。」イエスさまは、創世記でアダムとエバが創造されたときの記事を取り上げました。この頃はまだモーセの律法は与えられていません。その時から神さまは、男女の結婚を神聖なものとしておられました。
男女が結婚するのはそれぞれの意志、あるいは特に昔の場合には親の判断などによります。しかし、それでも結婚は神さまが2人を結び合わせたものだとイエスさまはおっしゃいます。だから、人間が勝手にそれを切り離してはいけない、それはどちらかが死ぬまで続くのだということです。
さらなる質問
(7節)彼らはイエスに言った。「それでは、なぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。」イエスさまの答えに対して、パリサイ人たちは「あなたの答えは、モーセの律法に矛盾しないか」と突っ込みます。
「モーセの律法では離婚が認められている。どういう理由でかという点については、2つの学派で意見が異なるが、とにかく離婚そのものは禁じられていない。あなたはモーセの律法の教えを理解していないのか?」というわけです。
離婚に関する律法の精神
(8節)イエスは彼らに言われた。「モーセは、あなたがたの心が頑ななので、あなたがたに妻を離縁することを許したのです。しかし、はじめの時からそうだったのではありません。アダムとエバが創造されたとき、夫と妻は対等な立場で助け合うパートナーでした。しかし、2人が罪を犯したとき、様々なものがおかしくなりました。そして、男女の関係も対等でなくなります。夫と妻は、どちらが相手を支配して思い通りに動かすかを争うライバルになってしまったのです。
(創世記3:16)また、あなたは夫を恋い慕うが、彼はあなたを支配することになる。」
- この「恋い慕う」という言葉は大好きという意味ではなく、「支配しようとする」という意味です(創世記4:7参照)。
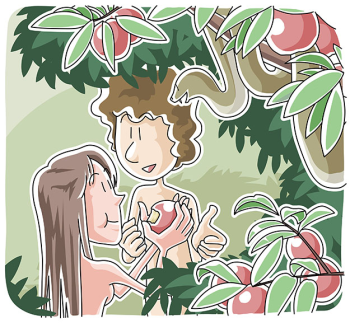
古代においては女性が働ける場所がほとんどなかったため、女性は子どもの頃から年を取るまで、父親・夫・息子の世話にならないと生きていけませんでした。結婚生活において、妻は夫に対して非常に弱い立場だったのです。もしも、些細な理由で離婚ができるとしたら、途端に女性は路頭に迷ってしまいます。
そこでモーセの律法では、女性を守るために離縁状を書いて離婚せよと命ぜられています。これはいつでも好きなときに離婚していいという許可の教えではなく、簡単に離婚できないようにするため、つまりは女性たちの立場を守るための教えなのです。
その律法の精神を無視して、離婚していい理由を議論することは全くの的外れです。イエスさまはそのことを指摘しています。そして暗に、神聖な神さまの命令を使って他人を陥れようとするパリサイ人たちの動機、その態度を批判していらっしゃいます。
結論
(9節)あなたがたに言います。だれでも、淫らな行い以外の理由で自分の妻を離縁し、別の女を妻とする者は、姦淫を犯すことになるのです。」イエスさまは、妻の姦淫以外に夫は妻を離縁することができないという立場です。
夫はさまざまな理由で妻を離縁するでしょう。しかし、その理由が妻の不貞でない限り、神さまの目にはその離婚は無効です。ですから、その男性が別の女性を妻に迎えたら、「妻がいるのに別の女性と関係を持った」ということになる。イエスさまはそうおっしゃっています。
つまり離婚問題に関してイエスさまは、表面的にはシャンマイ学派の主張の方に軍配を上げました。
だた、ヒレル学派の元になったラビ・ヒレル(紀元前1世紀の律法学者)は、当時のパリサイ人たちが律法をただ形だけ文字通りに守ることにこだわりすぎている点を批判した人です。神さまへの愛と隣人への愛の実現がモーセの律法の目的だと教えて、愛の実現という手がかりで律法の教えを解釈しなければならないと主張しました。
この点についてはイエスさまもまったく同じ立場です。ラビ・ヒレルは立派な考えを持っていたのですが、後継者たちは自分たちに都合のいい解釈を施すようになっていったのですね。
つまりイエスさまは、形式主義のシャンマイ学派も、いい加減なヒレル学派も、どちらも支持していらっしゃるわけではないということです。そしてどちらも、神さまへの愛、人への愛という大切な精神を忘れているよと指摘しておられるのです。
独身について
弟子たちの反発
(10節)弟子たちはイエスに言った。「もし夫と妻の関係がそのようなものなら、結婚しないほうがましです。」イエスさまとパリサイ人たちの議論を聞いていた弟子たちが、口を挟みました。夫と妻の関係が対等だというのなら、結婚しない方がましだと彼らは言います。弟子たちもまた、男尊女卑の考えに染まりきっていたのです。
独身者はスペシャルな人である
(11-12節)しかし、イエスは言われた。「そのことばは、だれもが受け入れられるわけではありません。ただ、それが許されている人だけができるのです。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また、人から独身者にさせられた人たちもいます。また、天の御国のために、自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は、受け入れなさい。」今でこそそういう風潮はなくなりましたが、昭和の時代には「独身者は社会的に未熟」と言われがちでした。イエスさまのこの言葉は、生涯独身でいるという立場は神さまによって許可された人だけが体験できる、特別なものだということです。
そしてイエスさまは、独身者には3種類いるとおっしゃいました。
- 生まれつき病弱だとか障がいを抱えているとかいう理由で、結婚できない人
(これは障がい者差別ではありません。古代では障がいがあると働けないことが多かったので、結婚して家族を養うことができませんでした) - 人から怪我をさせられたり、無理矢理去勢させられたりして、結婚できない状態にさせられた人
- 自ら進んで独身者でいることを選んだ人。その理由は、天の御国のため、すなわち神さまに仕えることにたっぷりと時間とエネルギーを使うためです。
まさに弟子たちはだだをこねているだけでした。「それを受け入れることができる人は、受け入れなさい」というイエスさまの言葉が、皮肉として突き刺さりますね。パリサイ人だけでなく、弟子たちも神への愛・隣人への愛というモーセの律法の目的を忘れてしまっていました。
それでは、ここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。
2.神への愛・人への愛を大切にしよう
神は私たちの動機を探られる
この話をお読みください。昔、横山幹雄牧師(となみ野聖書教会)が語ってくださった言葉が心に残っています。それは、「何が罪かを考えるより、どうしたらイエスさまに喜んでいただけるかを考えましょう」という言葉です。神さまは私たちの行動だけでなく、その行動の背後にある動機もご覧になっています。神さまに対する真実の愛、あるいは他の人に対する真実の愛から出ている行動なのか、それとも自己中心的な動機なのか、です。
何が罪かばかり考える生き方は、「どうやったら神さまに叱られないで、しかも自分の好きなことをやることができるだろうか」という、なんだか神さまの目を盗むような生き方につながりかねません。そのような態度は不健全であって、神さまとの良い関係を育てないどころか、むしろおかしくしてしまうでしょう。
川端光生牧師(キリストの栄光教会)が、著書「理屈っぽい人のQ&A要点ノート」の中でこんなエピソードを書いておられます。ある人が川端先生にこう尋ねました。「姦淫は罪ですね?」
先生はこう答えます。「その通り、妻以外の女性と関係を持つことは罪です」。
するとその人は重ねてこう尋ねました。「じゃあ、どうしようもない状況で関係を持ったとしたらどうですか? それでも罪になるのですか?」
川端先生は著書の中でこうおっしゃっています。「もし私が『どうしようもない状況ならしかたがありませんね』と答えたなら、きっとこの人は自分でそのどうしようもない状況を作り出して、姦淫に及ぶつもりだったのだろう」。
もしそういう心で「罪を犯さないようにしよう。いったい何が罪なのだろうか」と考えたとしても、すでにその人の心は神さまの方を向いていません。神さまとの関係が、最初からおかしくなってしまっています。だからすでに罪を犯しています。(当サイト「ショートエッセイ」より)
パリサイ人たちは、いい加減なヒレル学派の人たちだけでなく、表面的には文字通りモーセの律法を守ろうとしていたシャンマイ学派の人たちも、どちらも神さまや人への愛を忘れていました。イエスさまの弟子たちでさえそうでした。
聖書を読み、その命令を守ることは大切なことです。しかし、どういう心でその行動をしているか、いつも自己チェックをしましょう。
- もしかしたら、神さまを出し抜いて好きなことをしてやろうという思いがあるかもしれません。
- あるいは自分が立派な人間だということを周りの人にアピールして、ほめられたいという思いがあるかもしれません。
- あるいは他の人のことを神の命令を守らない罪人扱いして見下げることで、自分の立場を高めたいという思いがあるかもしれません。
神と人への愛を具体的に実現しよう
そして、今この瞬間、どのように行動したりどういう言葉を発したりすることが、愛を実現することなのか考えましょう。
神の愛を味わおう
ではどうしたら、私たちが神さまや人への愛を実現できる存在になれるのでしょうか。それは、私たちが神さまの愛を体験することによってだと聖書は教えます。(第1ヨハネ4:10, 19)私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、宥めのささげ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。…(中略)…私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
パリサイ人たちも弟子たちも、神さまの命令を心から喜んで受け入れてはいませんでした。むしろ、自分たちの自己中心的な欲望を優先させていました。神さまはそんな彼らを直ちに滅ぼすこともおできになりましたが、忍耐強く彼らが悔い改めて正しい生き方をするのを待ってくださいました。
またイエスさまは、何度も離婚と再婚を繰り返したサマリアの女性を責めませんでした。そして姦淫の現場で捕まった女性のことも赦されました。
私たちに対しても、神さまの恵みの愛が注がれています。ともすれば不純な動機で行動してしまう私たちですが、そんな私たちがイエスさまの十字架によって赦され、清められ、神さまの愛を受けるのにふさわしいと言っていただけている。そのことをいつも感謝しましょう。
それが私たちを正しい動機、すなわち神さまへの愛、人への愛に基づく行動へとかき立てる原動力です。